英語では、セミコロン(;)という記号が様々な場面でよく使われます。
日本ではあまり馴染みのない記号ですが、皆さんは、このセミコロンが何を意味するか、ご存じでしょうか?
この記事では、英語でのセミコロンの使い方やルール、コロンとの違いなどを詳しく分かりやすくご紹介しています。
この記事を読むことで英語のセミコロンに関する疑問は全て解決されるでしょう。
IELTSや英検、TOEIC、TOEFLといった技能試験でもよく見かける記号なので、しっかりその意味や使い方を知っておきましょう。
今まで英語の試験なども何度も受けてきたぼくが、今回は英語のセミコロンについて分かりやすく説明していきます。
英語のセミコロンとは
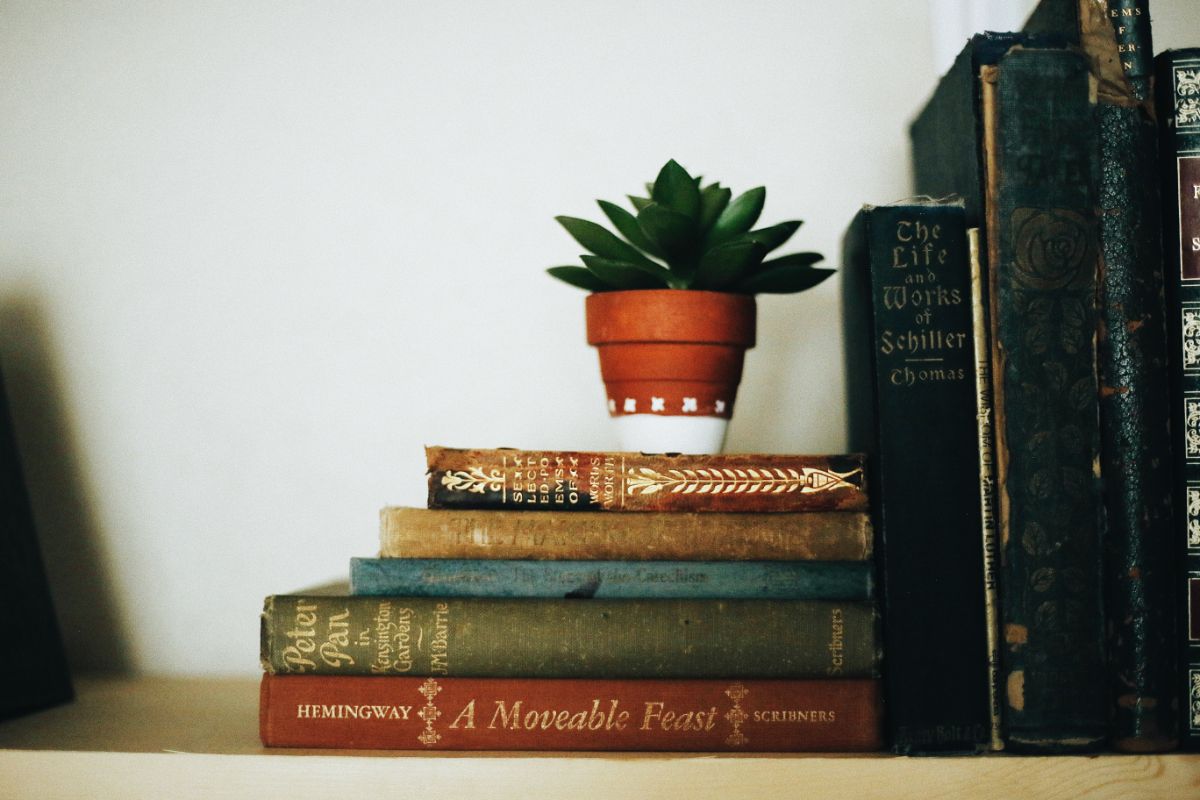
セミコロン(;)とは、2つの文章を接続するときに使われる句読点です。
コンマとピリオドのちょうど中間のような役割を持ちます。
このセミコロンには、文章を休止するという役割があり、伝えたいことをはっきりさせたいときや、文章に注目を与えたいときに使用されます。
また、セミコロンを使うことで、読みやすい、またすっきりとした文章にすることができます。
ただし、その使い方にはルールがあり、誤った使い方をすると、反対にわかりにくい文章になってしまうので注意が必要です。
セミコロンの使い方とルール

セミコロンには、大きく分けて3つの使い方があります。
こちらでは、セミコロンの使い方とルールをご紹介したいと思います。
接続詞として使う
1つ目のセミコロンの使い方は、接続詞としての使用です。
ただ接続詞といっても、全ての接続詞の役割を持っているのではなく、前後の関係性が強い、もしくは前の文章を説明する接続詞として使います。
日本語の「また、そして、だから、つまり、すなわち」などがこれに当たります。
例えば、
Taro was sick.
太郎は体調が悪かった。
Taro didn’t go to school yesterday.
太郎は昨日学校へ行かなかった。
という2つの文章があるとき、一般に「太郎は、体調が悪かったから学校に行けなかった」と考えることができますよね。
そのため、この2つの文章は、「~から(理由)」にあたるsoを間に置くことで、1つの文章にすることができます。
体調が悪かったから、学校に行かなかった。
このとき、接続詞の代わりにセミコロンを使っても、2つの文章を繋ぐことができます。
Taro was sick; he didn’t go to school yesterday.
これが1つ目のセミコロンの使い方です。
文法上のルールとしては、Taro was sick , so he → Taro was sick; he というように、コンマと接続詞を省いて、代わりにセミコロンを打ちます。
またセミコロンで繋いだ文章は1文となるので、セミコロンに続く文字は小文字となります。
The dog is calm, and it is also friendly.
この犬は穏やかで、フレンドリーだ。
- ○ The dog is calm; it is also friendly.
- × The dog is calm; and it is also friendly.
- × The dog is calm; It is also friendly.
2つの文章を繋ぐときに使う
2つ目の使い方は、独立した文章を繋いで、1つの文章として意味を持たせるときの使用です。
下の文章を例に見てみましょう。
雨が強く降った。試合が中止になった。
この2つは、お互いに独立した文章ですが、もし雨が原因で試合が中止になったのなら、therefore(したがって)やas a result(その結果)といった言葉を補うと、1つの文章として意味を持つようになりますよね。
雨が強く降った。したがって、試合が中止になった。
ただこれらの文章はどちらも短く、1つのした方が読みやすかったりすると思います。
そんなときは、(このthereforeなどを接続副詞と言いますが)接続副詞の前にセミコロンを置いて、文章をまとめることができます。
こうすることで、関係性を強調したロジカルな文章となります。
It rained hard; therefore, the game got called off.
また接続副詞の後のコンマがいらないと感じた場合は、取り除いても大丈夫です。
It rained hard; therefore the game got called off.
いくつものリストをまとめるときに使う
3つ目のセミコロンの使い方は、リストをまとめるときの使用です。例えば、訪れたことがある県を、東北地方、関東地方、九州地方というように地方別で紹介するとします。
東北地方は、北海道と宮城県に行ったことがあります。関東地方は、東京都、千葉県、神奈川県に行ったことがあります。九州地方は、福岡県と熊本県に行ったことがあります。
とこのように、文章を分けて書いても問題はありませんが、セミコロンを使えば、読みやすく1つの文章にすることが可能です。
セミコロンを置き方は、大きなカテゴリー(ここで言う地方)ごとに置きます。
セミコロンで大きく分けるという感じですね。
東北地方では、北海道と宮城県(;)関東地方では、東京都、千葉県、神奈川県(;)九州地方では、福岡県と熊本県に行ったことがあります。
また、セミコロンは連続する動詞を分ける場合にも使えます。
この本は、文章の作成方法(;)エッセイの書き方、見直し方、書き直し方(;)データの分析方法をご紹介しています。
コロンとの違い
見た目がセミコロンと似ている記号に、コロン(:)がありますが、意味は大きく異なります。
セミコロンは文章を繋ぐときに使うとご紹介しましたが、コロンは、何かを説明するとき、列挙するとき、引用するときに使用します。
つまり、まずメインの文があって、コロンを置いた次の文で補足する、といった使い方をします。
例えば、ウィキペディアにあるペンギンの定義を見てみましょう。
ペンギンとは、水生の飛ばない鳥のグループです。ペンギンは、ほぼ南半球でのみ生息しています。
この文章は、コロンを使うと以下の形に書きかえることができます。
ペンギン:ほぼ南半球でのみ生息する、水生の飛ばない鳥のグループ
また、名詞を並べるときにもコロンを使用できます。
日本では、以下の県に行ったことがあります: 北海道、宮城県(東北地方)東京都、千葉県、神奈川県(関東地方)福岡県、熊本県(九州地方)
ここでは、文章を繋ぐ記号をセミコロン、定義や引用、名詞の列挙に使う記号をコロンと覚えておくと分かりやすいかなと思います。
リストに関しては、セミコロンとコロンの使い分けが少しわかりにくいですが、大きな区分がいくつかある場合はセミコロン、1つの区分に名詞をずらりと並べる場合はコロンを使います。
日本語への訳し方
セミコロンが使われている文章を、日本語に訳す場合はどうすればいいのでしょうか。
実際のところ、セミコロンはこのように訳すというルールはありません。
文脈に沿って、意味がしっかり伝わるように訳すのが最も自然な文章になると思います。
場合によっては、接続詞をこちらであてがってもいいと思います。
それと同じく、接続詞を無理に加える必要もありません。
例えば、
明日ショッピングセンターに行こう。週末は人が多いらしいよ。
という文章は、人が多いのが嫌だから明日(= 平日)ショッピングセンターに行くのか、人が多い方がいいから明日(= 週末)ショッピングセンターに行くのかがわかりません。
そのため、無理に接続詞をつけるより、そのままセミコロン以外を訳した方がいい場合もあります。
まとめ
以上がセミコロンの意味と使い方になります。セミコロンは、関連する文章をリンクさせる句読点です。
このセミコロンを使用することで、文章が読みやすくなったり、伝えたいことを伝えやすくなったりします。
試験対策としてもそうですが、実際に使うために知っておくのも、きっといつか役に立つはずです。セミコロンがある文章は、sophisticated(洗練)されて見えるらしいですよ!



